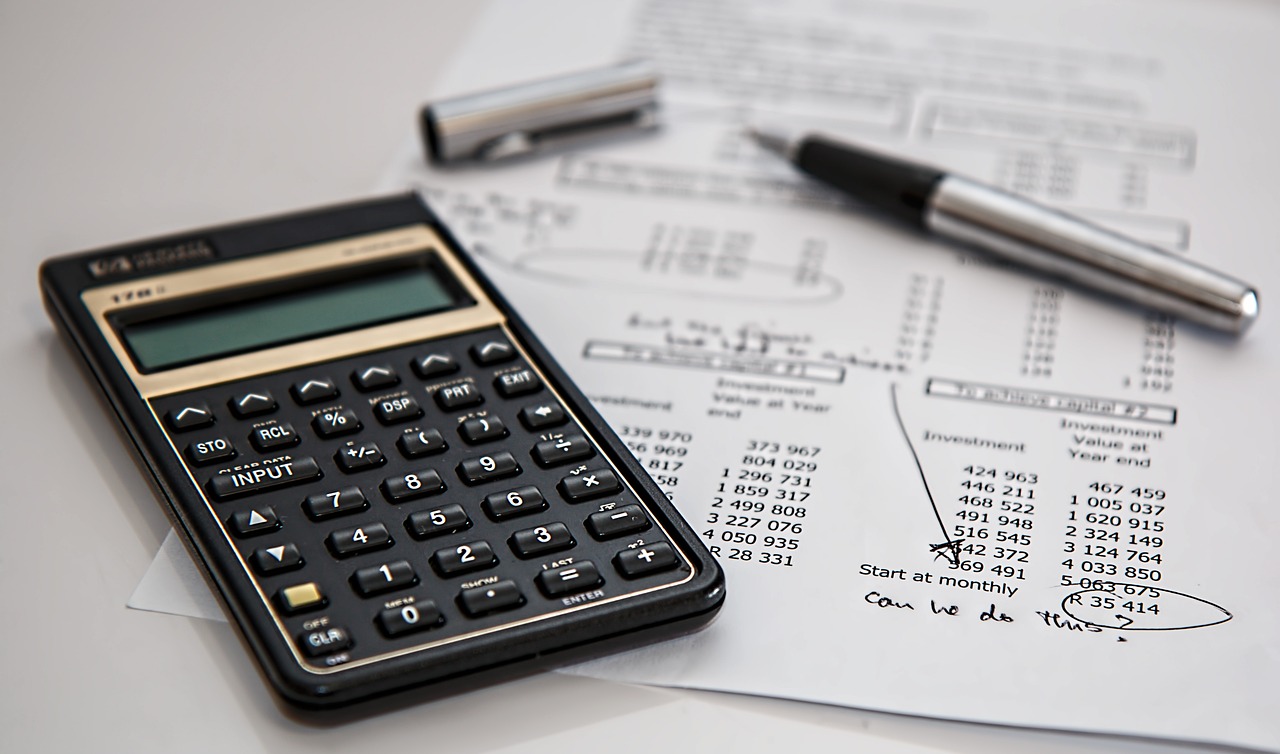
1. 本稿の目的と射程
本稿は、連載第1回(実務総論)で示した M&A 実務上のバリュエーション・フレームを前提に、タイ/ベトナム/インドネシア/インドの4ヵ国について、(1) 通貨選択とWACC設計、(2) 為替リスク(対称/非対称)実装、(3) 会計・開示差を踏まえたコンプス共通化、(4) 小規模上場・限定的カバレッジ環境での予想値運用、を実務手順として整えることを目的とする。各国の数値は市場・時点・業界で振れが大きいため、以下のレンジ・例示は方法論の提示にとどめ、個別案件では最新の前提の再推計が必要である点に留意されたい。
2. 国別分析に先立つ共通枠組み
2.1 通貨選択(名目/実質)
CF通貨とWACC通貨は一致させるのが原則である。新興市場では名目で組むほうが運用上は現実的であることが多い。名目CF×名目WACCを基本線とし、インフレの水準・トレンドが高い場合は価格転嫁のラグと運転資本回転の通貨感応度をモデル化するほうが再現性が高いとみられる。
2.2 WACC構成
- Re = Rf + β × MRP + CRP (+ Size/ESG 追加)
- WACC = E/(D+E) × Re + D/(D+E) × Rd × (1 − 税率)
CRP(カントリーリスクプレミアム)は、ソブリン・規制・法執行・外資規制・資本移動・税制一貫性・通貨制度等の定性を反映した上乗せとして設計するのが実務的である。βは可能ならローカル上場ピュアプレイのアンレバードβを複数取得し、メディアンを採用するアプローチがノイズ耐性に優れると考えられる。
2.3 為替の対称/非対称
対称型は感応度で十分なことが多いが、非対称(下方テール肥大)が想定される構造(外貨建て負債比率が高い、原材料USD連動×売上ローカル、価格転嫁ラグが長い等)では、WACC上乗せ+CF側確率シナリオの両建てが望ましい。CF側ではショック幅×発生確率×継続期間を明示しておくほうが経営陣合意を得やすいとみられる。
2.4 小規模上場・限定的カバレッジへの対応
ASEAN・インドの相当部分では、上場企業でも小規模が中心でアナリストカバレッジが限定的、かつEarnings Guidanceが開示されない場面が少なくない。東洋経済のような日本特有のデータソースは当該地域では前提にならないため、会社開示+独自のドライバー仮説で予想を組み、DCF×マルチプルのクロスチェックでレンジ整合を取るのが現実的である。
2.5 Global WACC と Local WACC:通貨整合の原則
バリュエーションにおける**通貨の一貫性(Currency Consistency)**は前提設計の中核である。原則は単純で、キャッシュフロー(CF)の通貨と資本コスト(WACC)の通貨を一致させるべきである。
- Local WACC:ターゲット事業の現地通貨建てCFを割り引く際の現地通貨建てWACCである。運転資本・価格転嫁・税金・金利など、ローカル要因がCFに強く作用する場合に適合しやすい。
- Global WACC:USD建て(またはEUR等)で管理されたグローバルCFを割り引く際のグローバル通貨建てWACCである。原材料・売価・契約・ヘッジが実質的にUSDに連動する場合や、買い手グループのマネジメントモデルがUSDベースのときに整合的とみられる。
注意すべきは、Local CFにGlobal(USD)WACCを当てること、またはその逆を行うことは通貨ミスマッチを招き、インフレや為替の取り扱いが二重化/欠落化するリスクが高い点である。CFとWACCの通貨は必ず一致させる。
2.6 Damodaranモデルの位置づけと注意点(USD→現地通貨変換)
Damodaranモデル(グローバルERP+カントリーリスクプレミアム(CRP)等を用いる一連の実務フレーム)は、USDベースの資本コスト推計を迅速に組み上げる際に有用であるとみられる。一方で、そのまま現地通貨建てのCFへ適用することは適切ではない。通貨と資本コストの一致が要件であり、USDベースで求めた資本コストは現地通貨ベースに変換する必要がある。
2.6.1 通貨変換の基本式(名目→名目)
USD建ての名目資本コスト rUSDrUSD を、現地通貨(LC)建ての名目資本コスト rLCrLC へ変換する近似は、期待インフレの比を用いた以下で表せる。
1+rLC≈(1+rUSD)×1+πLC1+πUSD⇒rLC≈(1+rUSD)1+πLC1+πUSD−11+rLC≈(1+rUSD)×1+πUSD1+πLC⇒rLC≈(1+rUSD)1+πUSD1+πLC−1
- πLC,πUSDπLC,πUSD は期待インフレ率であり、過去CPIではなくフォワード(もしくはブレークイーブン)に基づくのが望ましい。
- この変換はWACC全体、あるいは**Re(株主資本コスト)やRd(負債コスト)**の名目金利要素に適用しうる。
- 実質→名目の二段階(実質USDコスト→実質LCコスト→名目LC化)で行っても同値になる。
2.6.2 実務上の落とし穴(よくある誤り)
- 通貨ミスマッチ:LCベースのCFにUSD WACCを当てる、またはその逆を行う。
- CRPの二重計上:ReにCRPを積み上げ、同時にCF側で「国リスク減額」を重ねるなど、WACCとCF両側で同じ国リスクを重複反映する。
- Rfの取り扱い:USDリスクフリー(U.S. Treasuries)でReを算出した後、単純にLCの税率やβを混ぜると不整合が生じやすい。Rfは通貨別に整えるか、USDで完結→インフレ換算でLC化する。
- インフレの取り違え:直近CPIの実績を期待インフレの代替とし、高インフレ局面で過大/過小な換算を招く。可能であれば市場インプライドの期待インフレを参照する。
- 負債コストの通貨:LCで借りるのか、USDで借りるのかの資金調達通貨構成とヘッジ方針に応じてRdを通貨別に設計し、最終WACC通貨に合わせて加重する必要がある。
2.6.3 変換の最短手順(例示)
- 前提:USD名目Re=11.0%、USD期待インフレ πUSDπUSD=2.5%、現地期待インフレ πLCπLC=6.0%。
- 変換:
rLC≈(1+0.110)×1+0.0601+0.025−1=1.110×1.034146−1≈0.1489 (≈14.9%)rLC≈(1+0.110)×1+0.0251+0.060−1=1.110×1.034146−1≈0.1489(≈14.9%)
- WACCは、Re(LC)とRd(LCの税後)を目標D/Eで加重して最終化する。通貨・名目/実質の一貫性を再確認する。
2.7 実装プロトコル(Global/Localの選択とチェック)
- CF通貨の決定:売価通貨、原材料通貨、契約通貨、ヘッジ方針を踏まえ、CFをUSDで組むのかLCで組むのかを先に決める。
- WACC通貨の決定:CF通貨と同一通貨で設計する(Global WACC=USD、Local WACC=LC)。
- Rfの構築:
- LCルート:LC国債利回り−デフォルトスプレッド補正(又は無リスク代理)
- USDルート:U.S. Treasuries+CRP(国リスク)→インフレ換算でLC化
- ERP/CRP:ERPは通貨中立の考え方も取りうるが、CRPは国固有であり重複計上を避ける。
- βの推計:ローカル上場ピュアプレイのアンレバードβメディアンを推し、最適D/Eでレバード化。
- Rdの設計:資金調達通貨・満期構成とスプレッドで求め、税後に調整しWACC通貨で加重。
- 最終チェック:名目/実質、通貨、インフレ、CRP、ヘッジの一貫性を点検。CF側の為替シナリオとWACC側のCRPが二重化していないかを確認する。
3. タイ(THB)
3.1 規制・会計・開示の示唆
上場はIFRS準拠であり、IFRS 16によるオペリースのオンバランス影響をEBITDA・Net Debt双方で共通化する必要がある。英語/タイ語の二言語開示が中心で、セグメント情報の粒度は会社差があるとみられる。
3.2 通貨選択とWACC
名目THBベースが運用上は自然である。Rfは長期国債利回り、MRPはグローバル・ローカル双方の市場リスクを参考値とし、CRPは法制度の安定・通貨政策・外資規制の程度を勘案して上乗せする設計が一般的である。D/Eは業界平均よりも**ターゲットの最適構造(Tax Shieldと可処分CFの安定性)**を尊重するほうがよいだろう。
3.3 為替リスク
原材料USD連動×売上THBの製造・消費財では、USD高/THB安局面の非対称がCF側に出やすい。価格転嫁ラグ(月数)と在庫回転をドライバーに、−10%ショック×発生確率×転嫁完了までの期間をCF側で明示的に織り込むアプローチが説明適合的である。
3.4 コンプス共通化
- IFRS16:EBITDA増とリース負債認識を共通化し、EV/EBITDA比較の歪みを抑える。
- 減損:営業損益に計上される影響は非経常としてバックアウト。
- 非支配株主:少数持分が厚いコングロマ系ではEV/Equityブリッジの注記を強化する。
3.5 ケーススケッチ(仮定)
- 正常化EBITDA 9.0、WACC(THB名目) ≈ 10–11%、CF側ショック:USD高10%×20%×3ヶ月。
- Implied EV(DCF中央値) = 80、EV/EBITDAレンジ 8–10x → 72–90。中央値整合は概ね良好。
- Equityブリッジ:EV 80 − Net Debt 12 ± NWC反転 +1 → Implied Equity ≈ 69。
4. ベトナム(VND)
4.1 規制・会計・開示
多くの企業がVAS(Vietnamese Accounting Standards)で開示しており、IFRS移行は今後進むとみられるが移行度は会社差が大きい。オペレーティングリースや関連当事者取引の注記粒度はまちまちであり、EBITDAの3つのCによる正規化の重要度が高いと考えられる。
4.2 通貨選択とWACC
名目VNDでのモデル化が現実的である。Rfはローカル国債利回り、βはローカル上場ピュアプレイからアンレバードを採るが、薄商いとボラによるノイズが大きいためメディアン+補正を推奨する。CRPは法制度の運用・為替制度・資本移動の慣行を加味して上乗せする。
4.3 為替リスク
USD原材料×VND売上の構造では、非常時の下方テールが在庫評価・粗利率に非対称的に作用しやすい。CF側でショック幅×確率×在庫回転期間+価格転嫁ラグを明示し、在庫評価差損の一時性と粗利率の正常化速度を別トラックで表現すると、議論が収束しやすいとみられる。
4.4 コンプス共通化
- 会計基準差:VAS→IFRS相当へのブリッジ(リース、減損、のれん、引当)を作業仮説として設定。
- EBITDA正規化:役員報酬、保険料、オペリース/レンタル、一過性費用をCore/Controllable/Continuousで整理。
- マルチプル:EV/EBITDA・EV/EBIT中心に、IFRS16影響の共通化を明示。
4.5 ケーススケッチ(仮定)
- 正常化EBITDA 6.5、WACC(VND名目) ≈ 12–14%。
- Implied EV(DCF中央値) = 55、EV/EBITDAレンジ 7–9x → 45.5–58.5。
- Equityブリッジ:EV 55 − Net Debt 8 ± NWC反転 +0 → Implied Equity ≈ 47。
5. インドネシア(IDR)
5.1 規制・会計・開示
会計は**PSAK(IFRSコンバージョン)**であり、IFRS16影響の取り扱いはIFRSに近似していると理解される。上場開示は英語/インドネシア語の二言語が多く、セグメント・関連当事者・オフB/Sの注記は会社差がある。
5.2 通貨選択とWACC
名目IDRでのモデル化が自然である。Rfはローカル長期国債、βはローカル/近接ピュアプレイのアンレバードβメディアンを採択し、CRPはコモディティ比率・規制・資本移動等を反映して上乗せする。金利サイクルの変動幅が大きい局面では、ターム構造を織り込むシナリオを併置すると整合的である。
5.3 為替リスク
輸入原材料USD連動や外貨建て債務の比率が高い場合、非対称ショックが資金繰り・財務費用に同時発現する可能性がある。CF側で粗利率シナリオと財務費用シナリオを相関付きで走らせると、リスク説明が現実に近づくと考えられる。
5.4 コンプス共通化
- IFRS16共通化、減損の非経常バックアウト。
- 非支配株主が厚い持株構造はEV/Equityブリッジの注記強化。
- 倍率はEV/EBITDA/EV-EBITをベースに、資源感応業界では**EV/EBITDA(在庫/サイクル補正後)**を用いる選択肢がある。
5.5 ケーススケッチ(仮定)
- 正常化EBITDA 8.0、WACC(IDR名目) ≈ 12–13%。
- Implied EV(DCF中央値) = 70、EV/EBITDAレンジ 7.5–9.5x → 60–76。
- Equityブリッジ:EV 70 − Net Debt 18 ± NWC反転 +1 → Implied Equity ≈ 53。
6. インド(INR)
6.1 規制・会計・開示
Ind ASはIFRSに収斂しており、Ind AS 116(リース)、Ind AS 36(減損)等の取扱いはIFRSに準じる。FDI規制、FEMA、RBIガイドラインはディールのストラクチャや価格レンジに影響しうるため、既存株譲渡か増資か、コンディショナル条項を早期に検討するのが実務的である。開示は英語中心で粒度は相対的に高いが、業界によっては入札競争が強くマルチプルが張り付きやすいとみられる。
6.2 通貨選択とWACC
名目INRが基本である。Rfはインドルピー建て長期国債、βはローカル上場ピュアプレイのアンレバードβメディアンを採択、CRPは制度運用・税制一貫性・通貨サイクル・ガバナンスの指標を材料に上乗せを設計する。ITサービス/製薬・CDMO/消費D2Cなどは、成長プレミアムによりEV/EBITDAが先行する局面がありうる。
6.3 為替リスク
輸入原材料USD依存や外貨建て借入の比率が高い場合、粗利率と財務費用に非対称ショックが同時に波及する可能性がある。CF側で粗利率−1.0pt×確率と財務費用+x bps×確率を共時に組み込み、価格転嫁の速度とヘッジ方針をシナリオ分岐する構成が説明的である。
6.4 コンプス共通化
- Ind AS 116影響をEBITDA・Net Debtに共通化。
- 減損は非経常としてバックアウト。
- 非支配株主はEV/Equityブリッジに厳密反映。
- 倍率はEV/EBITDA・EV/EBITに加え、IT/ソフトウェアではEV/売上を補助指標として参照する選択肢がある。
6.5 ケーススケッチ(仮定)
- 正常化EBITDA 12.0、WACC(INR名目) ≈ 12–13%。
- Implied EV(DCF中央値) = 120、EV/EBITDAレンジ 10–12x → 120–144。
- Equityブリッジ:EV 120 − Net Debt 10 ± NWC反転 +0 → Implied Equity ≈ 110。
- ストラクチャ:増資30の併用でEV拡張余地あり。ただし希薄化でImplied Equity配分が変化するため、プレ・ポスト資本構成を併記するのが望ましい。
7. クロスカントリーでのコンプス共通化プロトコル
- IFRS16/Ind AS116/VAS→IFRS相当のリース影響を共通化(EBITDA・Net Debt双方)。
- 減損・一過性のバックアウトで継続収益力に揃える。
- 非支配株主をEV/Equityブリッジに厳密反映。
- セグメント差(B2B/B2C、輸出内生比率、コモディティ感応度)を補助注記で平準化。
- 倍率の主指標はEV/EBITDA・EV/EBIT、テック系はEV/売上を補助。
- ローカル通貨倍率とUSD換算倍率を併置し、為替期ズレの影響を注記。
- レンジ提示(メディアン+四分位)で単点依存を回避。
8. 為替リスク実装テンプレート(対称/非対称)
- 対称型:±5%/±10%の感応度を売上・粗利・OPEX・CapEx・NWCに伝播。EBITDA感応度とFCF感応度を図示。
- 非対称型:
- ショック幅:例)−10%(USD高)
- 発生確率:例)20%
- 持続期間:例)3ヶ月(四半期)
- 転嫁ラグ:例)2ヶ月
- 在庫回転:例)60日
- 外貨建債務感応:例)財務費用+x bps
これらをCF側に確率加重で実装し、WACC上乗せは残余リスクの補正として位置付けるのが整合的と考えられる。
9. 国別チェックリスト(抜粋)
共通:通貨整合(名目/実質)、CRP根拠、為替の非対称性、IFRS16共通化、減損/一過性除外、非支配株主、Equityブリッジ、レンジ提示。
- 上場:会社開示+ドライバー仮説で売上/粗利/運転資本/CapExを作成し、DCF×マルチプルでレンジ整合。
- 非上場:トップダウン(市場規模・浸透率・成長率)×ボトムアップ(SKU、店舗、生産能力、受注残)の統合でUnlevered FCFを構築。
- 感応度:WACC/為替/マージンのトルネードを掲示し、どの入力が価値に効くかを可視化。
- CF通貨とWACC通貨は一致している(Global=USD/Local=LC)
- USDベースのRe/Rdを期待インフレ比でLCへ換算した(式2.6.1)
- ERP/CRPの二重反映がない(WACC側とCF側で重複していない)
- Rdは調達通貨構成と税率に整合している
- CRPの根拠(制度・通貨体制・資本移動等)は注記されている
11. 付録:モデル断面の標準化(数式・定義)
- NOPLAT=EBIT×(1−実効税率)
- Unlevered FCF=NOPLAT+減価償却−CapEx−運転資本増減
- WACC=E/(D+E)×Re+D/(D+E)×Rd×(1−税率)
- Re=Rf+β×MRP+CRP(+Size/ESG)
- 企業価値=事業価値+非事業資産+現預金(非事業資産は時価評価&税効果)
- Equity=EV−純有利子負債±運転資本反転±その他調整
- Implied EV/Implied Equity:手法から逆算された事業価値/株式価値
12. まとめ
国別の違いは通貨・CRP・為替構造・会計・開示の掛け算である。定量の「見かけの差」をそのまま倍率差に転写するのではなく、IFRS16・減損・非支配・VAS/PSAK/Ind ASブリッジを通じて同一土俵を作り、名目通貨の一致と非対称リスクのCF側実装で再現性を高めるのが要諦である。小規模上場・限定的カバレッジ環境では、独自ドライバー仮説+レンジ提示が信頼性の核となるだろう。
次回(第3回)は**業界編(食品・飲料/消費財、物流、製造)**を予定し、EBITDAの3つのCによる正規化、運転資本/CapExの粒度、IFRS16影響の倍率比較をより実務的に掘り下げる。